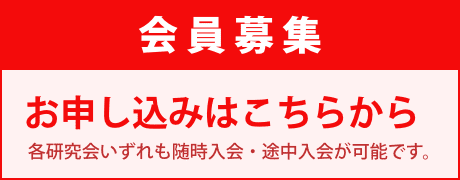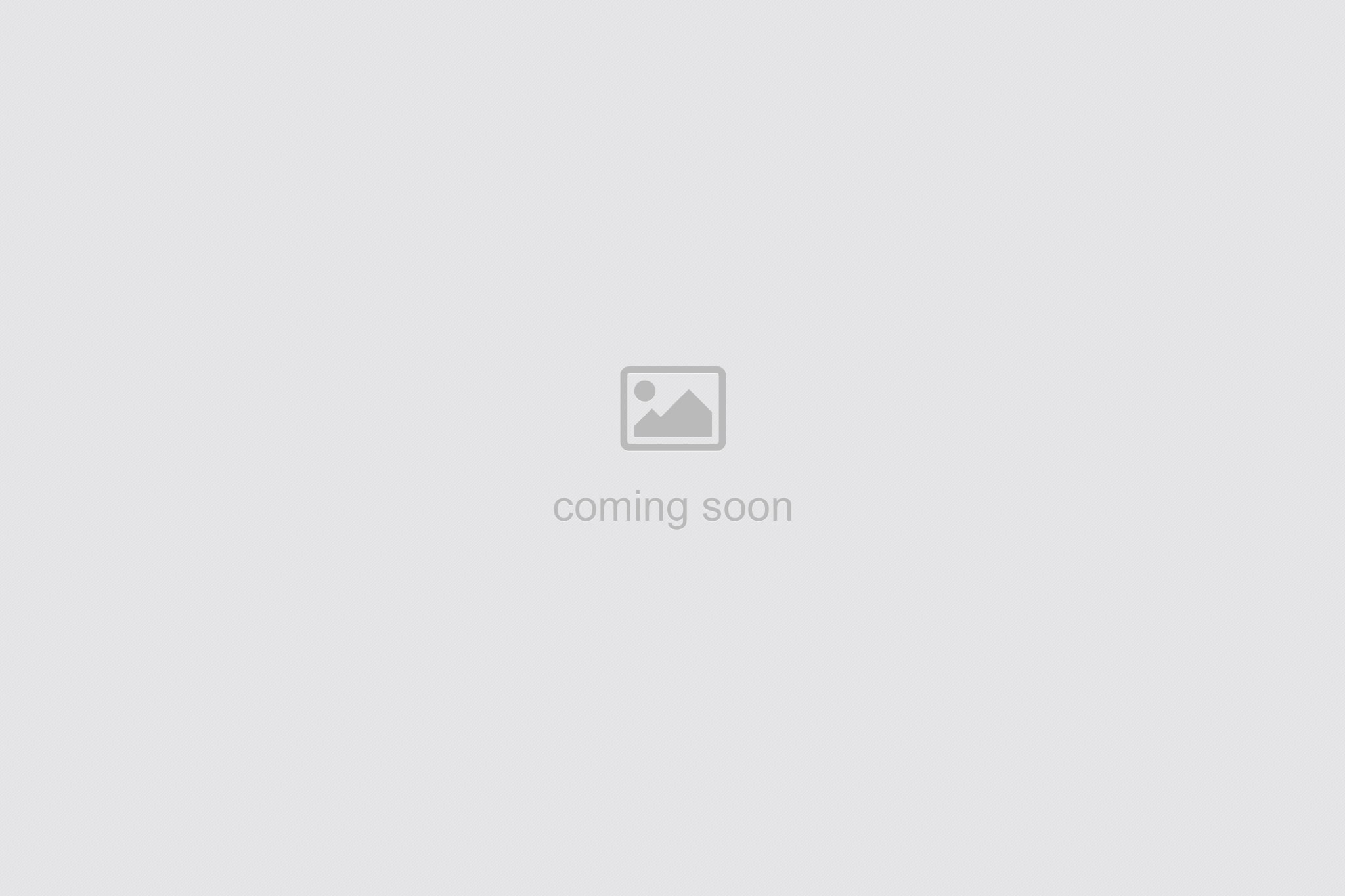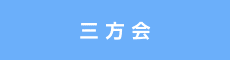自動車とモビリティの未来を考える研究会 【2021年度は終了致しました】
通称『自動車研』(現在の「自動車とモビリティの未来を考える研究会」)は、故下川浩一先生(法政大学名誉教授)を始祖とし、下川先生、藤本先生、河野先生を中心に、経営研究所の看板的また異色の研究会として長きにわたり、業界発展とモノづくり研究に大いなる貢献を頂きましたが、2022年3月末日をもって一区切りとし、2022年4月より、経営研究所の外郭組織的な位置づけになる「自動車問題研究会(会長 藤本隆宏先生)」に統合することに相成りました。
さて自動車問題研究会(自問研)は、自動車産業を取り巻く様々な問題・課題について広い視野に立って勉強し、お互いの交流を図ることを目的とした任意団体であり2019年に50周年を迎えました。現在、会員は主要自動車メーカー、サプライヤー各社、銀行、証券、調査会社、大学、研究機関などから200名超となります。定期的なセミナーに加え、工場見学&新車試乗会、モーターショー見学会や、懇親会、忘年会では、セミナーの講師と会員同士の交流、情報交換を活発に行ってまいりました。皆様のご参加をお待ち申し上げております。
連絡先:jimonken.tokyo@gmail.com
年間プログラムの印刷
年間プログラム(2021年度) (553KB) |
研究会の概要
自動車・パーソナルモビリティ産業においては、「100年に一度」と言われる変革期(ただし今後20年は続く)と言われて久しいですが、我々は、これに対する辻褄の合った全体像をいまだ得ていません。CASE(Connected, Autonomous, Sharing, EV)という覚えやすいキーワードが提示されていますが、これとても相互に複雑に絡み合った連立方程式の様相を呈しており、C/A/S/Eを個別問題にバラして、都合の良い話にみを取り出し、内外のメディアの潮流に乗っているだけでは、この長期問題の本質は見えてきません。
例えば、COVID-19感染拡大により、感染防止的な自家用車通勤が再注目され、カーシェアリングには逆風が吹いています。2020年初までは想定外だった変数が加わったわけです。
サステナブル・デジタル・グローバルな未来の産業像を知るためには、自動車、モビリティのみならず、産業全般、ICT、半導体・AI、サービス化など、広範囲な分野のトップ専門家の御意見を聞きつつ、最終的には、我々自身が、全体シナリオを主体的に考えていく必要があります。本研究会では、質の高い定例会講演をベースとしつつ、そこで終わりとせず、主催者側も関与して「持続可能な全体像」を皆様と一緒に議論していきたいと考えております。
例えば、COVID-19感染拡大により、感染防止的な自家用車通勤が再注目され、カーシェアリングには逆風が吹いています。2020年初までは想定外だった変数が加わったわけです。
サステナブル・デジタル・グローバルな未来の産業像を知るためには、自動車、モビリティのみならず、産業全般、ICT、半導体・AI、サービス化など、広範囲な分野のトップ専門家の御意見を聞きつつ、最終的には、我々自身が、全体シナリオを主体的に考えていく必要があります。本研究会では、質の高い定例会講演をベースとしつつ、そこで終わりとせず、主催者側も関与して「持続可能な全体像」を皆様と一緒に議論していきたいと考えております。
期間、日程と時間(全11回,8月休会)18:30~20:00(オンライン)
第268回 2021年04月21日(水) | 「MaaSの現在と未来」 牧村 和彦氏(一般財団法人計量計画研究所 理事) |
第269回 2021年05月19日(水) | 「デジタル/脱炭素などの流行り言葉の裏にある半導体産業の動向等から 探る自動車産業へのポストコロナの影響見込み」 安井 公治氏 (三菱電機株式会社 FAシステム事業本部 産業メカトロニクス事業部 主席技監) |
第270回 2021年06月 休会 | ※6月16日に開催を予定しておりました6月例会は延期させて頂きます。 岩城富士大様には12月以降にご登壇いただく予定です。 尚、6月例会休会に伴う振替日は8月18日と致します。 |
第271回 2021年07月21日(水) | 「モビリティを取り巻く競争軸の変質:「製品開発」から「社会設計」へ」 東 秀忠氏(山梨学院大学経営学部 教授/山梨学院経営学研究センター センター長/ 一般社団法人ものづくり改善ネットワーク 特任研究員) |
第272回 2021年08月18日(水) | 「自動運転技術の現状とその未来社会への導入に向けた課題と期待」 菅沼 直樹氏(金沢大学 高度モビリティ研究所 副所長・教授) |
第273回 2021年09月15日(水) | 「ブリヂストンにおけるCASE・IoTに関わる取り組み」 真玉 修司氏(株式会社ブリヂストン 事業開発共創戦略部 主査) |
第274回 2021年10月20日(水) | 「令和トランスフォーメーションにおける自動車産業の果たすべき役割」 鈴木 裕人氏(アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 パートナー) |
第275回 2021年11月17日(水) | 「歴史的なAUTOSAR標準の事例を題材に、オープン標準とビジネスモデルについて考える」 立本 博文 氏(筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授) |
第276回 2021年12月15日(水) | 「次世代モビリティの経済学:マーケットデザインによる制度設計」 栗野 盛光氏(慶應義塾大学 経済学部教授 マーケットデザイン研究センター長) |
第277回 2022年1月19日(水) | 「中国電動化シフトの最前線~政策・市場の変化、電池の争奪戦及び日本企業の対応」 湯 進氏(上海工程技術大学客員教授) |
第278回 2022年2月16日(水) | 「ソフトウェアの真のボトルネックは何か? 大規模ソフトウェア開発における人中心の品質マネジメント革新」 岸良 裕司氏(株式会社ゴールドラットジャパン CEO) |
第279回 2022年3月16日(水) | 「「監視」ネットビジネスの衝撃 」 西口 敏宏氏(一橋大学名誉教授 武蔵大学客員教授) |
前年度(2020年度)「自動車とモビリティの未来を考える研究会」テーマ一覧
「アフタ―コロナ時代における日本企業のサプライチェーン」 藤本 隆宏(東京大学大学院経済学科教授 経営研究所長) |
「KINTOが描く未来のモビリティサービス」 本條 聡氏(株式会社 KINTO 副社長執行役員) |
「世界のバーチャルエンジニアリング実態と日本の課題 ~IT /Digital 技術「駆使」の開発とモノづくり~ 」 内田 孝尚氏(東京電機大学 工学部 非常勤講師/一般社団法人日本機械学会 フェロー/元本田技術研究所シニアエキスパート) |
「コンソーシアムベースの標準化プロセス:AUTOSARを事例とした2段階集合行為モデルに関する試論」 糸久 正人氏(法政大学社会学部 准教授/ペンシルバニア大学ウォートン校 客員准教授) 藤本 隆宏(東京大学大学院経済学研究科 教授) |
「米中ディカップリングとグローバルサプライチェーンの再構築」 柯 隆氏(公益財団法人東京財団政策研究所 主席研究員) |
「IoT/AI 技術の活用。つながるクルマとモビリティ・サービスの未来」 村澤 賢一氏(日本アイ・ビー・エム株式会社 AI Applications 事業部 事業部長) |
「トヨタのスポーツでの取組み」 廣田 利幸氏(トヨタ自動車株式会社 スポーツ強化・地域貢献部 部長) |
| 「電池の覇者 -車載電池業界の攻防と次世代電池の行方-」 佐藤 登氏(名古屋大学 未来社会創造機構客員教授 エスペック株式会社 上席顧問) |
「ポストコロナの自動車産業の長期展望 -ニューノーマルに着目した産業構造変化を論じる-」 中西 孝樹氏(株式会社ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト) |
「自動車の電動化に関わる将来展望」 大聖 泰弘氏(早稲田大学名誉教授 次世代自動車研究機構研究所 顧問) |
| 「日本のモビリティスタートアップの挑戦 〜規制、コロナ、大企業との協業の視点から考える〜」 髙原 幸一郎氏(株式会社 NearMe 代表取締役社長) |
コーディネータ ・オブザーバー紹介
藤本 隆宏
経営研究所所長。東京大学名誉教授。早稲田大学教授。東京大学経済学部卒業、三菱総合研究所を経て、ハーバード大学ビジネススクール博士号取得(D.B.A.)。一般社団法人ものづくり改善ネットワーク代表理事。研究分野は技術・生産管理論、進化経済学。
<主な著書>Product Development Performance, Harvard Business School Press(共著、邦訳『製品開発力』ダイヤモンド社)、『生産システムの進化論』(有斐閣)、The Evolution of a Manufacturing System at Toyota, Oxford University Press、『マネジメント・テキスト 生産マネジメント入門(I・II)』、『日本のもの造り哲学』『ものづくりからの復活』(いずれも日本経済新聞出版社)、『建築ものづくり論』(共編著、有斐閣)、『現場から見上げる企業戦略論』(角川新書)Industries and Disasters(共編著、NOVA),ほか。
<主な著書>Product Development Performance, Harvard Business School Press(共著、邦訳『製品開発力』ダイヤモンド社)、『生産システムの進化論』(有斐閣)、The Evolution of a Manufacturing System at Toyota, Oxford University Press、『マネジメント・テキスト 生産マネジメント入門(I・II)』、『日本のもの造り哲学』『ものづくりからの復活』(いずれも日本経済新聞出版社)、『建築ものづくり論』(共編著、有斐閣)、『現場から見上げる企業戦略論』(角川新書)Industries and Disasters(共編著、NOVA),ほか。
青島 矢一
一橋大学イノベーション研究センター教授・センター長。1996年マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院博士課程修了。Ph.D.(経営学)。一橋大学産業経営研究所専任講師、一橋大学イノベーション研究センター准教授を経て、2012年3月より現職。専門はイノベーションのマネジメント。これまで、イノベーション過程における資源動員の正当化プロセスや、技術・産業・企業能力の共進化メカニズムに注目して、デジタルカメラ産業、半導体産業、先端材料産業、環境・エネルギー産業を含む様々な企業の事例分析を行ってきた。近年は、大企業とスタートアップ企業のコラボレーションによるイノベーション創出に関する研究を進めている。<主な著書>『ビジネス・アーキテクチャ:製品・組織・プロセスの戦略的設計』(共編著、有斐閣)、『競争戦略論』(共著、東洋経済新報社)、『メイドインジャパンは終わるのか:奇跡と終焉の先にあるもの』(共編著、東洋経済新報社)、『イノベーションの理由:資源動員の創造的正当化』(共著、有斐閣),『イノベーションの長期メカニズム:逆浸透膜の技術開発史』(共著、東洋経済新報社)ほか。
西野 浩介
三井物産戦略研究所産業情報部産業調査第一室シニア研究フェロー。専修大学非常勤講師。長銀総合研究所、日本デルファイオートモーティブシステムズを経て現職。米ケースウエスタンリザーブ大学経営大学院修了(M.B.A.)<主な著書・論文>『日本の金型産業をよむ』(工業調査会)、「中国自動車産業の課題と展望」『戦略研レポート』、「日本のエレクトロニクス産業-危機に直面する産業から読み取れるもの-」『戦略研レポート』、「世界で強化される自動車燃費規制とその影響」『戦略研マンスリー』ほか。
河野 英子
横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授。長銀総合研究所を経て、早稲田大学大学院商学研究科博士課程修了(博士(商学))、東京富士大学を経て現職。<主な著書・論文> 『ゲストエンジニア:企業間ネットワーク・人材形成・組織能力の連鎖』白桃書房、「関係的組織能力をベースとした競争優位の構築プロセス:日本発条の多角化事業成功の事例」『組織科学』、「研究開発型企業における社会的支援と成果管理:浜松ホトニクスの事例」『赤門マネジメント・レビュー』、「多角化を支える弱いつながりの形成とその強化:東海部品工業の医療機器事業参入の事例」『赤門マネジメント・レビュー』ほか。
横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授。長銀総合研究所を経て、早稲田大学大学院商学研究科博士課程修了(博士(商学))、東京富士大学を経て現職。<主な著書・論文> 『ゲストエンジニア:企業間ネットワーク・人材形成・組織能力の連鎖』白桃書房、「関係的組織能力をベースとした競争優位の構築プロセス:日本発条の多角化事業成功の事例」『組織科学』、「研究開発型企業における社会的支援と成果管理:浜松ホトニクスの事例」『赤門マネジメント・レビュー』、「多角化を支える弱いつながりの形成とその強化:東海部品工業の医療機器事業参入の事例」『赤門マネジメント・レビュー』ほか。
ダニエル・ヘラー
中央大学国際経営学部特任教授。<主な著書>. Heller, D.A. (2018) Industries and Disasters: Building Robust and Competitive Supply Chains, New York: Nova Science (藤本隆宏との共編著)、Heller, D.A. (2017) “Monozukuri Management: driver of sustained competitiveness in the Japanese auto industry,“ in Nakano, T. (Ed.) Japanese Management in Evolution: New Directions, Breaks, and Emerging Practices, London: Routledge, pp. 107-126 (藤本隆宏との共著)、ヘラーD.A. (2013)『収益力と競争力の両立:日系自動車メーカーの実績と今後の挑戦』信州大学イノベーション研究・支援センター、研究叢書4(共著)。
今までご参加いただいた企業の一部
いすゞ自動車、NEC、 NTTコミュニケーションズ、関東自動車工業、 小松製作所、ジヤトコ、 住商アビーム自動車総合研究所、損害保険ジャパン日本興亜、テクノバ、デンソー、トヨタ自動車、豊田自動織機、 日産自動車、日産車体、UDトラックス、日立製作所、日野自動車、富士重工業、ファースト、 ピアレス、本田技研工業、本田技術研究所、マツダ、三井住友銀行、三井物産戦略研究所、三菱ケミカル、三菱総合研究所、三菱電機、ヤマトホールディングス(株式会社省略)